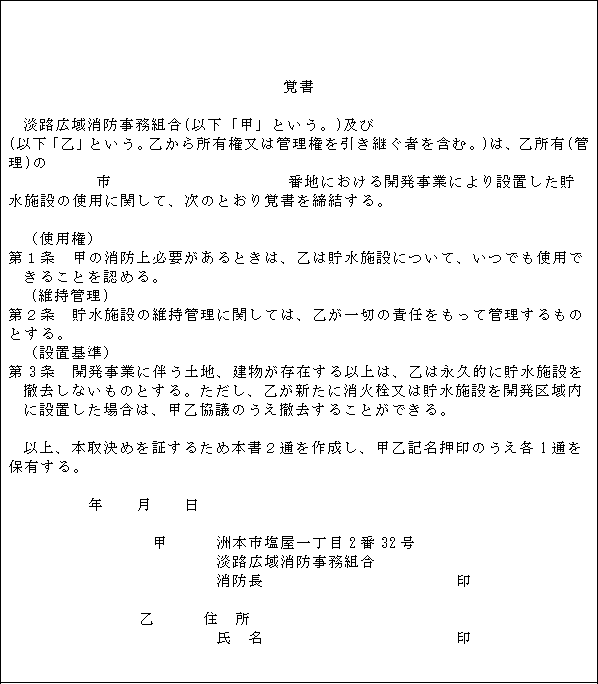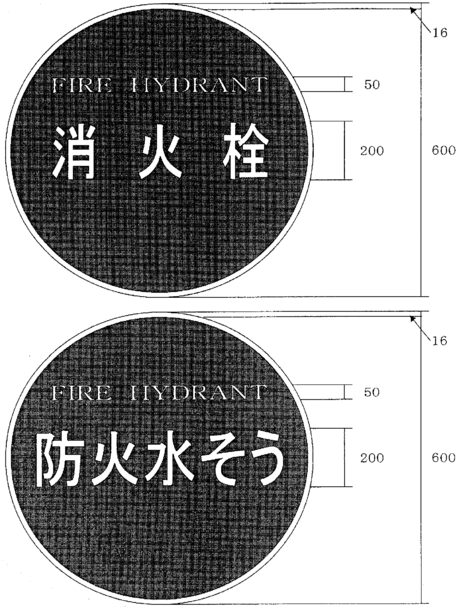○淡路広域消防事務組合開発行為等に伴う消防水利等の指導基準
平成16年11月24日告示第2号
淡路広域消防事務組合開発行為等に伴う消防水利等の指導基準
(目的)
第1条 この基準は、淡路広域消防事務組合(以下「当組合」という。)の管轄区域内で開発事業等を行おうとする事業者に対し、消防に必要な水利等が十分でない場合に設置する消防水利及び消防自動車の進入路等の計画に適切な指導を行うことにより、災害に強いまちづくりを図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この基準に掲げる用語の定義は、次の各号によるものとする。
(1) 「開発事業」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物について、同条第13号の建築をする行為をいう。
(2) 「事業者」とは、開発事業を行おうとする者をいう。
(3) 「開発区域」とは、開発事業を行う土地の区域をいう。
(適用範囲)
第2条 この基準は、当組合の管轄区域内で行われる開発事業で、都市計画法第29条に基づく開発許可及び良好な地域環境を確保するための地域社会建設指導要綱(昭和47年兵庫県告示第1613号)の適用範囲に該当する開発事業その他消防長が特に必要と認めたものについて適用する。
(消防水利の種類)
第3条 この基準により設置する消防水利は、原則として「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)による防火水槽及び消火栓とする。ただし、将来にわたって常時支障なく使用可能な状態で十分な維持管理及び安全管理が確保されるプール、遊水池等で、消防長が認めた場合は、消防水利とみなすことができる。
(消防水利の設置個数)
第4条 消防水利の設置個数は、既設水利も考慮に入れ開発区域全体を包含できるよう次により算定する。
要件 | 開発区域のすべての部分から、いずれかの消防水利に至る水平距離 | |
用途地域等 | ||
市街地又は準市街地 | 近隣商業地域、商業地域 | 80メートル以下 |
工業地域、工業専用地域 | ||
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 100メートル以下 | |
市街地又は準市街地以外の地域でこれに準ずる地域 | 140メートル以下 | |
備考 1 用途地域区分は、都市計画法第8条第1項第1号に規定するところによる。
2 市街地、準市街地については、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号及び第2号に規定するところによる。
2 消火栓を用いる事業者は、当該消火栓に給水することとなる水道事業者と別途協議を行うこと。
3 消火栓及び防火水槽を設置完了後、寄付行為等により管理を当該市町へ移管しようとする事業者は、当該市町担当者と事前に協議を行うこと。
4 高台及び急傾斜地等における開発事業においては、状況により別途協議を行う場合がある。
5 消防水利が5箇所以上必要となる場合、消火栓と防火水槽の比率は消火栓4に対し防火水槽1を原則とする。
(消防水利の位置)
第5条 消防水利の位置は、次の各号によるものとする。
(1) 消防自動車が2メートル以内に容易に部署することができ、かつ、水利の周囲に縦横2メートル以上の空地があること。
(2) 設置場所は、開発区域全体を考慮して消防活動上効果的な場所であること。
(消防水利の給水能力)
第6条 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものとする。
(防火水槽の規格及び構造)
第7条 防火水槽の規格及び構造は、次の各号によるものとする。
(1) 貯水量は40立方メートル以上の原則地下式とし、その構造は第8号に掲げるものを除き、鉄筋コンクリート造有蓋とし、漏水防止が完全になされていること。
(2) 水槽底の深さは、底設ピットの部分を除き地表面から4.5メートル以内であること。
(3) 吸管投入孔は、原則として内径0.6メートル以上の円形とし、2箇所以上設けること。
(4) 吸管投入孔の直下に深さ0.5メートル以上の「ストレーナー入れ」ピットを設けること。
(5) 水位が低下した場合に、呼び径25A以上の配管により自動的に給水できる装置を設けること。
(6) 採水口式の場合は、呼称75ミリメートルの単口式とし、吸水配管は鋼管若しくはそれと同等以上の強度を有するものを使用すること。なお、立上がり管については、鋼管径100ミリメートル以上とし、点検のための吸管投入孔と同様のマンホールを1箇所以上設けること。
(7) 上載荷重、自重及び土かぶり荷重、土圧、地下水圧、内水圧及び浮力に対する強度を有し耐久性があること。
(8) 二次製品防火水槽は、消防庁長官又は消防庁長官が指定した者(財団法人日本消防設備安全センター)が認定したものであること。
(消火栓の規格)
第8条 消火栓は、次の各号によるものとする。
(1) 消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の配管に取り付けられていること。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、配管口径を75ミリメートル以上とすることができる。
(2) 消火栓口(町野式金具)は、蓋面より30センチメートル以内とすること。
(消防水利の標識及び道路標示)
第9条 消防水利の標識及び道路標示は、次の各号によるものとする。
(1) 消防水利の標識の規格及び図案等は、別図のとおりとすること。
(2) 標識は、消防車両から容易に発見できる場所で、水利の取水場所から5メートル以内のところに設置すること。
(3) 防火水槽、消火栓の蓋又はその周辺部には、容易にはく離しない黄色の塗装を行うこと。
(消防水利等の維持管理)
第9条の2 消防水利等の維持管理については、次の各号によるものとする。
(1) 消防水利等を管理する者は、定期的に点検して良好に維持管理し、故障、破損等した場合は、速やかに修理及び復旧すること。
(2) 修理及び復旧に長時間を要する場合は、管轄する消防署へ報告すること。
(3) 事業者(市が管理するものを除く。)が管理する貯水施設にあっては、覚書(別記様式)を締結すること。
(消防隊進入路の確保)
第10条 開発区域内の道路は、消防車両の通行に支障となる植樹、アーチ、渡り廊下、空中架線等がないこと。尚、次条の空地に至る進入路等の幅員は5メートル以上とすること。
(消防活動用空地の確保)
第11条 予定建築物が3階以上又は最高の軒の高さが10メートル以上の場合で、特に梯子車等が接近して活動できるような空地が必要であると認める場合は、幅6メートル、長さ10メートル以上の消防活動空地(バルコニーがある場合は、バルコニー側)を確保すること。また、活動空地にはその旨の標示を行うものとする。
2 活動空地の面は平坦であり、消防車等の車両がすべり、めり込み等の現象を起こさない堅固な構造とし(梯子車専用活動空地にあっては、20トン以上の耐圧地盤とする。)、空地等が傾斜している場合は勾配を7パーセント以下とするものとする。
(基準の特例)
第12条 この基準の規定は、消防長が当該開発区域及び周辺地域の状況、予定建築物の位置、構造及び設備の状況から判断して、火災の発生及び延焼の恐れが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときは適用しないことができる。
(補則)
第13条 この基準に定めるものの他必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この基準は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日告示第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月21日告示第2号)
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行前に設置した消防水利については、改正後の基準に適合し、設置したものとみなす。
(淡路広域消防事務組合火災予防事務処理規程の一部改正)
3 淡路広域消防事務組合火災予防事務処理規程(平成19年訓令第149号)の一部を次のように改正する。
第29条に次の1項を加える。
5 当該開発事業に伴い設置した消防水利を撤去(変更)する場合は、廃止(変更)届(様式第32号の2)を提出するよう指導するものとし、受理した場合は、事務経理簿に必要事項を記載するとともに受付印を押印し、内容を確認して返付するものとする。この場合必要により現地確認を行うものとする。
様式第32号の次に次の1様式を加える。
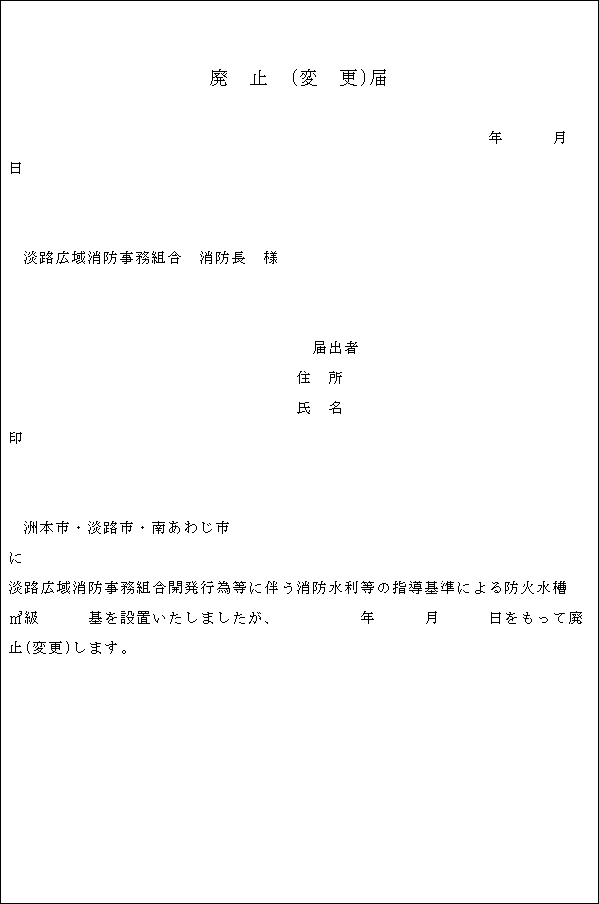
別図
消防水利の標識
|
(備考)1 数字は、ミリメートルを示す。
2 色彩は、文字及び縁を白色、地を赤色とする。
3 標示板は、GLより1m以上の高さに取付けること。